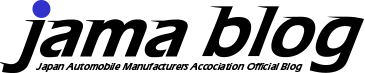- 2025/08/01
- JAMAGAZINE, イベント, バイク, レース, 今さら聞けない

【今さら聞けない】シリーズ 「鈴鹿8耐」用語
「鈴鹿8耐」は、正式名を「FIM世界耐久選手権〝コカ・コーラ〟鈴鹿8時間耐久ロードレース」といい、三重県の鈴鹿サーキットで毎年夏に開催されます。国内最大級の二輪車耐久ロードレースで、1台のバイクを2~3人で交代しながら走り、8時間でコースを何周できるかを競います。長時間走行するため、タイヤ交換や給油の作業時間をいかに短くするか、どのタイミングでピットインさせるか等、チームワークやレース戦略が勝敗を左右します。カワサキモータース、スズキ、本田技研工業、ヤマハ発動機の国内バイクメーカーのほか海外メーカーも参戦していて、今年は昨年を上回る55台がしのぎを削ります。
バイクファンには〝8耐〟でお馴染みですが、今年も決勝の日が迫ってきました。今や現地に行かずとも観戦できる時代ですが、迫力ある排気音やタイヤが焼ける臭い、観客の熱気などを五感で感じる興奮や一体感はリアル体験ならではの醍醐味です。遊園地やプール、温泉施設もある鈴鹿サーキットで長丁場のレースを楽しみましょう。今回の「今さら聞けない」は、初めて鈴鹿8耐を観る人のための用語解説です。
【クラス】
鈴鹿8耐に出場するマシンは、主に市販の4ストローク1000cc以下のバイクをベースに、耐久レース用に改造された車両です。具体的には、ヘッドライトの点灯義務、素早いタイヤ交換や給油を可能にする装置、冷却系システムの強化などが施されています。排気量や改造範囲には制限があります。
8耐で「クラス」と言えば、マシンの種類のことで、「EWC(世界耐久選手権)クラス」は市販車ベースで改造範囲を制限してあり、「SST(スーパーストック)クラス」はEWCよりさらに改造範囲が制限され、ほぼ市販車と同じとなっています。さらにスズキがカーボンニュートラル燃料などで参戦する実験的クラスとして設定される「EXP(エクスペリメンタル)クラス」もあります。
【トップ10トライアル】
「トップ10トライアル」は、予選2回目終了時点による上位10チームによって行われ、大会決勝のスターティンググリッド10位までを決めます。予選最速のライダー2人が参加し、1周のタイムを計測します。予選2回目までの結果で10位だったチームから走行を開始し、1位のチームが最後に出走。トップ10トライアルが終了した後に、各チームのライダー2名のラップタイムが合算され、大会の最終スターティンググリッド10位までが最終的に決定します。

【周回】
「インラップ」はピットインする直前の周回、「アウトラップ」はピットアウトしてからの最初の周回を指します。このインラップとアウトラップのタイムロスをいかに少なくするかが順位の近いライバルに競り勝つには非常に重要になってきます。8耐の場合、決勝レース直前にコースの状況を確認しながら走行、決勝開始40分前の午前10時50分からの1周を「サイティングラップ」と呼んでいます。
【ル・マン式スタート】
スタート前、コースの端に整列したライダーが、スタートの合図とともにコース反対側にあるマシンまで駆け寄ってスタートする方式です。名前の通り、もともとは自動車の「ル・マン24時間耐久レース」で行われていましたが、シートベルトの装着ミスやスタート直後の混乱といった安全面を理由に廃止され、名前だけが残っています。8耐では第1回からル・マン式が採用されています。
炎天下、レーシングスーツに身を包んだままスタートダッシュを強いられるライダーは大変ですが、この光景を見て「今年も8耐が始まった!」と興奮するファンも多いようです。ちなみに〝本家〟のル・マン24時間レースは今「ローリングスタート」が採用されています。スタート前の周回(フォーメーションラップ)の後、車両を止めることなく、そのまま加速していく方式で、スタート直後のクラッシュなどの混乱をできるだけ減らすのが主な狙いです。

もともと「割り当て量」「活動期間」という意味ですが、モータースポーツの世界では、スタートから最初のピットインを「第1スティント」、ピットアウトから再ピットインまでを「第2スティント」といった具合に、走行単位を指します。長丁場になる耐久レースでは、ライダーの体力やタイヤの摩耗、残燃料などを見極めてピット戦略を立てることが重要で、今の8耐では、上位チームは7回ピットの8スティント走行が一般的です。
8耐は一応、「耐久」という名前がついていますが、24時間レースと比べると走行時間はわずか3分の1ともいえます。車両性能の向上などもあって第1スティントから激しいバトルが繰り広げられ〝スプリント耐久〟と呼ばれるほどです。チームの戦略とともに、受け持ちのスティントをスロットル全開で走るライダーの気力やテクニックをぜひサーキットで感じてください。

【スペアマシン】
レーシングマシンは高価なパーツを丁寧に組み替えて作られていますが、その性能を極限まで酷使するため、トラブルはつきものです。可能ならピットで修復しますが、エンジンブローなど致命的な故障だったり、部品を交換するのに時間がかかり過ぎたりする場合、8耐では主催者の許可を得てスペアマシンに乗り換えることができます。このため、1チーム2台の車両を登録し、公式車検も済ませておきます。
四輪も含めてスペアマシンのことを「Tカー」とも呼びますが、由来ははっきりしていません。「テスト」「トレーニング」「テンポラリー(一時的な)」などの意味があるようです。ちなみに本番用マシンからスペアマシンに乗り換えるときは、「変更用手数料」が必要になります。

【ナイトセッション】
一般的にレースは日中に開かれ、夜間のレースは昼間とはまた異なるテクニックがドライバーやライダーに求められ、一方の観客にとっては独特な雰囲気を楽しめます。
午前11時半にスタートし、午後7時半にゴールを迎える8耐も夜間走行「ナイトセッション」が風物詩のひとつです。鈴鹿8耐を含むEWCのレースでは、2016年からヘッドライトの常時点灯が義務づけられていますが、鈴鹿8耐では慣例として、日没を迎えるとライト点灯を義務付けるサインが掲示され、観客がそれに応える形でライトスティックで会場を照らす「ライトオン」が名物となっています。
日中の蒸し暑さがやや和らぐ中、マシンのヘッドライトによる光がコース上を次々と流れ、観客が応援のため振るライトスティックも幻想的な風景を演出します。長丁場のレースではありますが、それだけに参戦者と観戦者の間には8時間を一緒に過ごした一体感があり、夜間のゴールは感動的です。ぜひ1度、体感してみてください。


【サステナブル燃料】
レースの世界もカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)と無縁ではありません。むしろ〝走る実験場〟として、さまざまなレースでカーボンニュートラル燃料が試されています。
カーボンニュートラル燃料は大きく「合成燃料」と「バイオマス(生物由来)燃料」に分けられます。合成燃料は二酸化炭素(CO2)と水素を合成して製造するもので〝人工的な原油〟と言えるでしょう。このうち、再生可能エネルギー由来の水素を用いた場合は「eフューエル」と呼ばれます。一方のバイオマス燃料は、植物などの有機資源を原料とした燃料です。どちらも使用時にはCO2を出しますが、これらの燃料はもともと大気中にあったCO2を原料としているため、地球全体としては「ニュートラル(中立)」というわけです。
8耐は一般的な燃料を使いますが、スズキは8耐を「サステナビリティに関する技術開発の一環」(鈴木俊宏社長)と位置づけ、環境に配慮した部品や燃料を用いた「GSX-R1000R」で参戦。カウルなど外装部品に再生材や自然由来の原料を混ぜるほか、燃料は「100%サステナブル」なものを使います。昨年は40%バイオ由来燃料で参戦し、総合8位入賞を果たしました。今年は100%サステナブル燃料とハードルを上げつつ、さらに上位を狙います。「チームスズキCNチャレンジ」に期待しましょう。

関連リンク