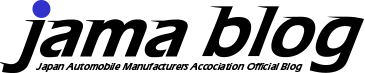- 2025/03/21
- JAMAGAZINE, その他, 思い出の一台

広報が選ぶ思い出の一台⑤「ロッキー」(ダイハツ工業)
JAMAブログを監修する各メーカー広報担当者が、クルマやバイクを好きになった、もしくは自動車業界に進もうと思ったきっかけとなった、あるいは業務で携わった「思い出の1台」をピックアップして熱く語ります。その第5回は、ダイハツ工業の近藤文彦さん。ダイハツブランドの情報発信を取りまとめる広報室のリーダーとして、日々業務に勤しんでいます。近藤さんの思い出の1台は、1990年に発売された初代「ロッキー」。その名称がいまも引き継がれている小型オフローダーです。
―初代「ロッキー」との出会いは
1997年に入社した時に、配属先職場の先輩から譲り受けました。「15万キロ近く走っているロッキーの買い替えを考えているけれど、乗ってくれるなら譲るよ?」という先輩からの言葉に、子供の頃から釣りが趣味だったので海や山に気軽に出かけられるオフローダーに憧れがあり、二つ返事で飛びつきました(笑)。ラダーフレームを採用した四輪駆動車で、悪路走破性に優れていましたので、暇さえあれば、サーフフィッシングやキャンプ、ウィンタースポーツを楽しむために雪山にも行きました。
学生時代に、軽自動車で毎日、通学していたこともあり、私にとって車は“生活必需品”でしたが、このロッキーによって、私の活動範囲や交流が大きく広がり、単なる道具ではなく、〝楽しい相棒“というイメージが加わりました。

ロッキーの思い出を熱く語る近藤さん
―記憶に残っているエピソードは
ロッキーを所有していた頃は会社の寮に住んでおり、同僚と一緒に乗る機会も多かったです。そんなある日、運転していた時に普段とは異なる振動をステアリングに感じました。大事に乗っていたのですが、15万キロ以上走っているクルマでしたので、不調が生じたようです。私にはその原因が分かりませんでしたので、仲の良かった開発部署の同期の友人に相談し、確認してもらったら、「ホイールのバランスが崩れていることが原因だね」とすぐに見抜いてくれました。私は、あまり自動車の構造に詳しくなかったこともあり、ステアリングの不調なので、当然、原因もステアリングにあると単純に考えていました。実際には、足回りから問題が生じて、その影響がステアリングに現れたことと、それをすぐに理解した技術者の友人に驚きました。自動車はさまざまな技術が一体となった集合体であり、多くの技術者の知識が凝縮されていることを知り、自動車の技術的な側面に関心を持ち、自分なりに調べ、学ぶきっかけになりました。
―初代ロッキー以降の愛車遍歴は
ロッキーの次はダイハツが1999年の東京モーターショーで市販モデルを公開した「ネイキッド」に乗りました。その後、スーパーハイト系の「タント」などを経て、いまは小型SUVの2代目「ロッキー」が愛車です。家族でキャンプや釣りを楽しんでいます。

再びロッキーに戻る
―さまざまな車を乗り継いできた経験が広報の仕事にどう生かされていますか
私の仕事の一つは、ダイハツ車の魅力を多くのユーザーに届けることです。ダイハツでは、お客さまに寄り添った〝良品廉価〟な、スモールカーづくりに取り組んでいます。主力となる軽自動車は、全国津々浦々で、男女問わず幅広い世代の方々にご利用いただいており、日常の買い物からレジャーや旅行など多様なシーンでご利用いただいております。こうした軽自動車の多面的な魅力を伝えるためには、生活必需品的な側面とともに、趣味的、技術的側面にも深く通じる必要があります。初代ロッキーと過ごした日々は、趣味性の高い車の良さと技術的な面での車の面白さを私に教えてくれました。また、さまざまな車と接してきたからこそ生み出せる説得力もあると思いますので、これからも、ダイハツの小さなクルマの魅力と、小さなクルマに込めたダイハツ技術者のこだわりや熱い想いを発信し続けていきたいと思います。

〈思い出の1台〉
1990年発売の小型オフローダー。ラダーフレームと四輪駆動の採用によって高い走破性能を実現した。脱着可能なレジントップを採用したことが最大の特徴で、ルーフを外すことでオープンカーの雰囲気も味わえた。オフローダーらしい力強さのあるネーミングはアメリカの西海岸にあるロッキー山脈に由来する。2019年に発売された小型SUVではその名称が約20年ぶりに復活し、話題を呼んだ。
関連リンク